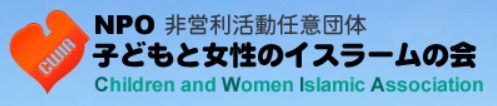「ムスリム・フレンドリー」と「ハラール」の違いについて(2)
結果として、、、
今回日本の各方面に問い合わせた時に感じたのは、「ムスリム・フレンドリー」というイスラーム教徒を対象にした食事のカテゴリーは日本人のためのものでした。ムスリムに配慮はしたいけれど、今ある日本のレストランのシステムはそのままで簡単に対応しましょうという、今現在の日本のシステムでムスリムの観光客に合わせた結果です。「ムスリム・フレンドリー」は日本以外ではあまり通用しない概念なのかもしれません。
日本を一歩出て世界標準に合わせると、全世界では、「ベジタリアン」・「 コーシャル」・「ハラール」のマークが主流で、それぞれに正当な承認機関や長い歴史的事実に裏付けされています。
多くの移民を受け入れているヨーロッパ・オーストラリア・アメリカでは「ムスリム・フレンドリー」というカテゴリーは行われていません。
私自身としてはこの「ムスリム・フレンドリー」を、「左前に着ている着物」の様だと感じています。一見すれば、遠くから見れば綺麗な和装に見えても、よくよく見てみれば、左側に着物を着た人は死人です。「ムスリム・フレンドリー」も一見「ハラール」の様であってもそれは「ハラール」ではありません。
ただ、「ムスリム・フレンドリー」にも、ムスリムが立ち合い、確認して限りなく「ハラール」に近いものが存在します。私達 、ムスリムにとってムスリムが関わっていることが、とても重要であるのです。
日本では少数派である私達「ムスリム・ムスリマ」は今や全世界で4人に1人といわれ、18億人とも言われています。日本の人口は1億2千万人。どちらの数が多いでしょうか?
「ハラール」の基準を決めるのは「日本人」ですか?「ムスリム」ですか?そして、「ハラール」は誰のために必要でしょうか?
これでは世界遺産となった「和食」の概念もいつか日本へ逆輸入する日が来ても、私達日本人は文句を言うことが出来ませんね。ムスリムであり、日本人である私はそれはおかしいと思います。皆さんはどの様に、お考えになりますか?ご意見をお寄せください。
参考文書
ニッスイアカデミー「食の禁忌」
http://www.nissui.co.jp/academy/eating/02/index.html
http://www.nissui.co.jp/academy/eating/02/02.html
http://www.nissui.co.jp/academy/eating/02/07.html
以上、今後不定期に続きます。